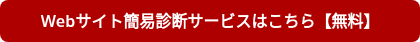Webサイトの成果を高めるためには、デザインの見た目や機能だけでなく、訪れたユーザーが「どんな体験を得られるか」という視点が欠かせません。この体験を指すのがUX(ユーザーエクスペリエンス)です。BtoB企業のWeb担当者がUXを理解しておくことで、改善点の方向性が明確になり、成果につながるサイト運用がしやすくなります。
本記事では、UXの基本からUIとの違い、BtoBサイトにおける重要性、改善の基本視点まで、初心者にもわかりやすく解説します。
目次
UX(ユーザーエクスペリエンス)とは
UXの定義
UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、ユーザーがサービスや製品を利用する中で得られる体験全体のことです。店舗での接客、製品の使い心地、アプリの操作感など、あらゆる接点での体験が含まれます。
- ネットショップで注文から配送までスムーズに進み、安心して買い物できた
- 家電を購入した際、説明書がわかりやすく使い方に迷わなかった
これらはいずれもUXの好例です。UXは、使いやすさや心地よさにとどまらず、「また利用したい」と感じられるかまで含めた体験全体を指します。ポイントは、迷わない・待たない・不安にならない、この3点です。
WebサイトにおけるUXとは
このUXの考え方は、Webサイトにもそのまま当てはまります。
WebサイトにおけるUXとは、ユーザーが検索やリンクから訪問し、情報を入手し、フォーム送信や資料ダウンロードなどの目的を達成するまでの一連の流れと、その中で得られる体験です。
- 製品情報が探しやすく、安心感があり、資料や事例にすぐアクセスできる
- ページの表示速度が速く、ストレスなく閲覧できる
- お問い合わせフォームが短く、入力しやすい
BtoB企業のWebサイトでこうした要素がそろっていると、ユーザーは満足感を得て、行動(お問い合わせや資料請求)につながりやすくなります。
UX・UI・CXの違いと関係性
UXとUIの違い
UXは、Webサイトやアプリといったチャネル内で、ユーザーが目的を達成するまでに得る体験全体を指します。UI(ユーザーインターフェース)は、その体験を支えるボタンやメニュー、フォーム、テキスト配置など、ユーザーとWebサイトがやりとりする接点とその設計です。
UI設計やデザインが整っていても、情報が探しにくい・導線が不明確・表示が遅いといった課題があると、UXの評価は下がってしまいます。逆に、デザインが多少古くても情報構造と導線が明快で、ユーザーが迷わずに目的を達成できれば、UXの評価は高まります。
UIとUXはどちらか一方だけで成り立つものではありません。UIの改善と全体設計の最適化を両立させることで、ユーザーが快適に利用できるWebサイトになります。
関連記事:UIの意味をわかりやすく|UXとの違いとWeb担当者が押さえるべき改善ポイント
UXとCX(顧客体験)の違い
UXはチャネル内の体験に対して、CX(カスタマーエクスペリエンス)は顧客と企業の関わり全体で積み上がる体験です。認知から検討、購入、利用、サポート、更新までを含みます。
例えばBtoBでは、Webサイト訪問から資料ダウンロードやお問い合わせに至るまでがUX、その後の返信メールや営業対応、導入後のサポートまでを含めた評価がCXにあたります。BtoBサイトは顧客と企業の最初の接点にもなりやすいため、ここで良い体験が生まれると後工程にも前向きな流れが生まれます。
このように、UIはユーザーとWebサイトの接点、UXはその接点がつながって生まれる体験、CXは営業やサポートまで含む企業やブランドとのやり取りを通した体験を指し、顧客との信頼を構築するためには、どれも欠かせない存在です。
BtoB企業のWebサイトにおけるUXの重要性
BtoB企業のWebサイトでは、UXを高めることが商談機会の最大化と成約率向上につながります。
BtoBサイトでUXが成果に直結する理由
BtoB企業のWebサイトを訪れたユーザーは、情報収集から比較、社内検討という複数ステップを経て意思決定に至ります。
この過程でUXの評価が低いと、次のような課題が起こります。
- 必要な情報が見つからず、競合サイトに移ってしまう
- Webサイトの掲載情報に信頼感が低く、社内で比較・検討の候補にならない
- お問い合わせや資料請求の導線が不明確で、行動に移れない
こうした状況は、せっかくの見込み客を失うことにつながります。Web担当者にとって、UX改善は単なる画面設計の話ではなく、自社全体の顧客体験の入り口を整える重要な役割でもあります。
関連記事:コーポレートサイトとは?BtoB企業が成果を出すための役割・設計・運用を解説
成果を高めるUX改善の3つのコツ
UX改善と聞くと難しく感じるかもしれませんが、基本のコツは3つに絞れます。
「迷わない・待たない・不安にならない」を意識してチェックするだけでも、ユーザー体験は大きく変わります。ここが整うと、検討のスピードが上がり、商談や成約につながりやすくなります。
迷わない
ユーザーが欲しい情報にまっすぐたどり着ける状態が理想です。ナビやカテゴリが直感的で、ページ内の見出しも分かりやすくしましょう。事例を業種別や課題別に整理しておくと、社内稟議の資料としても引用できます。
待たない
表示や操作でユーザーを待たせない状態です。ページの読み込み、スクロール、フォーム送信が重くないか確認しましょう。例えば、入力項目を必要最小限にし、エラー表示を分かりやすくすると途中離脱を防げます。
不安にならない
ユーザーが判断に必要な根拠がそろい、先の流れが見える状態です。実績データや事例、料金やセキュリティ、お問い合わせ後の案内などを明確にしましょう。「フォーム送信後の流れ」を一文添えるだけでも、次の行動への迷いが減ります。
この3つを意識して見るだけでも、自社サイトの課題や改善の方向性が見えてきます。次の章では、この考え方をもとに、UX改善を進めるために具体的にどこを確認すればよいかを整理します。
UX改善のチェックポイント
UX改善は大掛かりなリニューアルだけでなく、日々の見直しでも実現できます。ここではBtoBサイトのUXを考えるうえで、まず押さえるべき5つの視点を紹介します。
1.ペルソナの明確化
誰に向けたサイトなのかを定義すると、必要な情報やコンテンツの優先順位が見えてきます。例えば、実務担当者は具体的な機能やサポート体制、決裁者は投資判断のための信頼性や成果データを重視する傾向があります。
- 主要ターゲットは文言で明文化されているか
- ターゲットごとの導線が設計されているか
関連記事:【テンプレ付】BtoBペルソナの作り方とは?注意点と活用メリットを解説
2.情報構造とコンテンツ配置
情報量が多くても、分類や階層が整っていないと見つけにくくなります。カテゴリ分けや見出しの工夫で、最短ルートで目的情報にたどり着けるようにします。例えば、事例ページを業種別や課題別に整理すると、ユーザーが欲しい情報をすぐ見つけられます。
- 必要情報へ2〜3クリック以内で到達できるか
- 事例や資料は探したい項目で並べ替え・絞り込みができるか
3.バイヤージャーニーに沿った導線設計
訪問から目的達成までの行動シナリオを描き、それに沿って導線を設計します。
BtoBサイトでは「製品紹介 → 事例 → 資料ダウンロード → お問い合わせ」という流れが多く、この順序でスムーズに進めるかがポイントです。途中で必要な情報が抜けていたり、リンクが分かりづらいと、せっかくの見込み客が離れてしまいます。
- 資料DLやお問い合わせまでのステップ数は適切か
- ターゲットごとの導線が設計されているか
関連記事:バイヤージャーニーの基本と作成方法を解説!BtoBマーケに欠かせない理由とは
4.操作性と閲覧性の向上
見やすさ・使いやすさはUXの基本です。表示が遅い、スマートフォンでレイアウトが崩れる、フォーム入力が負担といった状況は、離脱理由になります。利用環境に関わらず快適に使える状態に整えましょう。
- 主要ページの表示速度に体感的な遅さがないか
- スマートフォンでの操作性とフォーム入力のしやすさは十分か
5.安心感を与える要素の設計
BtoBの商談は金額も大きく、意思決定に慎重になります。そのため、見込み客が「この会社に任せても大丈夫」と思える安心感が必要です。
常時SSLの対応や情報の最新化、第三者評価や受賞歴の掲載、導入企業ロゴの表示などは、取引先として安心感を与える要素となります。
- 実績や数値の出典や根拠は明確か
- お問い合わせ送信後の流れが示されているか
関連記事:ホームページ(Webサイト)リニューアルの進め方と成功事例
UX向上の第一歩は現状把握から
改善を始める前に、まず現状を正しく把握しておくと、改善の方向性が見えやすくなります。現状把握の方法には、大きく分けて次の2つがあります。
数値データによる分析
直帰率、離脱率、コンバージョン率など、アクセス解析ツールで確認できるデータから、離脱ポイントや停滞しているページを特定します。数値でユーザー行動の傾向を数値で客観的に分析することは、感覚では気付きにくい課題を洗い出すのに有効です。
例えば、資料請求ページには集客できているのにフォーム完了率が低い場合は「フォーム入力の負担が大きい」といった仮説が立てられます。数値を定点観測して推移を追えば、改善施策後の効果検証にもつなげられます。
ユーザー視点での確認
ヒートマップやユーザーテスト、社内での操作確認などを通じて、実際に使いにくい箇所や迷いやすい導線を洗い出します。
アクセス解析で直帰率や離脱率を確認したり、ヒートマップで迷いが生じている箇所を見つけたりすることに加え、社内の関係部署や普段あまりWebに触れていない人、操作に不慣れな人にも協力してもらうと、より幅広い気づきを得られます。さまざまな年代やデジタル経験の異なる人の視点が入ることで、本当に使いやすいかどうかを多角的に確認することができます。
関連記事:Webサイト改善点を洗い出す!課題抽出の基本ステップと4つの方法
どこに課題があるのかが分かれば、少ない工数でも効果的な改善手法を選択することができます。「まずは自社サイトのどこから見直すと良いか」を短時間で把握したい方に、無料のWeb簡易診断をご用意しています。
専門のアナリストが貴社のWebサイトを多角的に分析し、ユーザビリティ評価やSEO対策状況、コンバージョン最適化、さらには競合他社との比較など、幅広い観点から診断を行います。
診断結果は、わかりやすいレポートにまとめて提出し、Webサイトの現状課題と改善の方向性を提案いたします。ぜひ一度お試しください。
まとめ
UXは、ユーザーが製品やサービスを利用する中で得る体験全体を指します。特にBtoB企業のWebサイトでは、UXの質が商談化率や成約率に大きく影響する点を押さえておきましょう。
改善の第一歩は、現状を正しく知ることです。「迷わない・待たない・不安にならない」の観点で自社サイトを見直すことが大切です。
私たちタービン・インタラクティブでは、事業拡大に貢献するWeb戦略のご提案、サイト制作、CRMやマーケティングオートメーションの導入支援など多数の実績がございます。専門的なWebサイト診断や改善のご相談もお任せください。