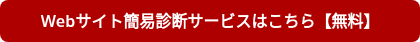Webマーケティングにおいて、コンバージョン(CV)は効果測定に欠かせない指標のひとつです。しかし、実際には「どの行動をコンバージョンに定義すべきか」「なぜコンバージョンが増えないのか」が不明確なケースも少なくありません。
この記事では、コンバージョンの基本から種類、設計や改善のポイントをわかりやすく解説します。
目次
コンバージョン(CV)とは?
コンバージョンは、Webマーケティングの成果
コンバージョン(Conversion)とは、英語で「変換」や「転換」を意味する言葉です。Webマーケティングでは、Webサイトを訪れたユーザーが「企業にとって望ましい行動をとる」こと、つまり「成果に変わる」ことを指します。
BtoB企業では「お問い合わせフォームの送信」「資料のダウンロード」「商品の購入」などがコンバージョンにあたります。これらはすべて、見込み客が興味関心に基づき具体的なアクションを行った状態です。
つまりコンバージョンとは、Webサイトがどれだけ成果に貢献しているかを示す、非常に重要な指標なのです。
なぜコンバージョン(CV)が重要なのか?
Webサイトのアクセス数だけでは、成果に結びついているかは分かりません。「見られている」ことと「行動につながる」ことは別だからです。
そのため、あらかじめ「どの行動を成果とみなすか」を定義し、コンバージョン(CV)という指標として設定しておくことが重要です。
また、コンバージョンは一つとは限りません。Webサイトでユーザーに達成してほしい行動の数だけ、複数設定することもあります。この場合、目的や優先順位は整理しておきましょう。
「ページ閲覧数は多いのに、お問い合わせが少ない」といった場合も、お問い合わせ以外のコンバージョンポイントを分析することで、ユーザーの行動を推測でき、ボトルネックとなる課題や改善の方向性を見出すこともできるのです。
BtoBサイトの目的に応じたコンバージョン設定例
ここでは、BtoB企業のWebサイトにおけるコンバージョン例を目的別にご紹介します。
BtoB企業では、見込み客の段階的な育成が必要になるケースが多いため、ホワイトペーパーのダウンロードやセミナー申込など、すぐに商談につながらない行動もコンバージョンとして設定することがあります。
重要なのは、施策ごとに「何をもって成果とするか」を明確に定義し、その指標をもとに改善を図ることです。また、KPI(重要プロセスの目標数値)としてCV数やCVRを設定する際も、このコンバージョン定義が基準となります。
関連記事:BtoBサイトで問い合わせ数を増やすには?成果が出る改善ポイント
コンバージョンの主な種類
コンバージョンの測定方法や考え方にはいくつかの種類があります。その都度、最適なコンバージョンを設定できるように違いを正しく理解しておきましょう。
総コンバージョン
期間内に発生したすべてのコンバージョンの合計数です。同じユーザーが何度コンバージョンしても、そのたびに1件としてカウントされます。
ユニークコンバージョン
1ユーザーあたり1回だけカウントされるコンバージョンです。複数回の行動があっても、重複せず実数を把握したいときに使われます。
クリックスルー・コンバージョン
広告をクリックしたユーザーが、その後コンバージョンに至った場合にカウントされます。広告効果を直接的に測る際に使われます。
ビュースルー・コンバージョン
広告をクリックせず閲覧だけしたユーザーが、あとでコンバージョンした場合にカウントされます。間接的な広告の影響を把握したいときに有効です。
広告施策でのコンバージョン評価と媒体による違い
広告におけるコンバージョンの定義は、一般的にはクリックスルー・コンバージョンが主要指標となり、ビュースルー・コンバージョンは間接的な効果として参照されます。
注意点として、広告媒体ごとの管理画面とGoogleアナリティクスでは、CV数に違いが出ることがあります。これはアトリビューションモデルの違いやCookie制限、タグの不備などが影響しています。広告施策に取り組む際は、どこで何をコンバージョンとして計測するのかを、しっかりと定めましょう。
マイクロコンバージョンの重要性、マクロコンバージョンとの違い
Webサイト上で発生するコンバージョンは、その性質や役割に応じて分類・分析することで、マーケティングの改善につなげやすくなります。
なかでも、ユーザーの行動ステップに着目して「どの段階でコンバージョンが発生したのか」を捉える視点は重要であり、その際に有効なのがマイクロコンバージョンという考え方です。
企業にとっての主要な成果となるアクションを「マクロコンバージョン」、その前段階にあたる行動を「マイクロコンバージョン」と呼びます。
「マクロコンバージョン」には資料請求やお問い合わせなど、直接的な商談や受注につながる行動が含まれます。
一方で「マイクロコンバージョン」は、その前段階にあるページ閲覧やホワイトペーパーのダウンロード、フォーム入力といった接点の行動を指します。
特にBtoBでは、検討期間が長く、一度の訪問でいきなりマクロコンバージョンに至ることは稀です。
そのため、マイクロコンバージョンをあらかじめ定義しておくことで、ユーザーの関心度や検討状況をより正確に捉え、適切な改善アクションにつなげることができます。
直接コンバージョンだけに注目するのではなく、「どのような経路や接点が間接的にマクロコンバージョンに貢献していたのか?」という視点を持つことで、コンテンツ設計やチャネル改善のヒントが見えてきます。
このように、マイクロコンバージョンを通じたユーザー行動の可視化は、マーケティング施策全体の最適化にも役立ちます。
関連記事:アクセス解析でわかることとは?サイトの改善点をみつける分析ポイント
コンバージョン率(CVR)の考え方と業界比較
CVRとは?基本の計算式と使い方
コンバージョンに関連してよく使われる用語が「CVR(Conversion Rate)」です。対象者のうち、どれだけの割合がコンバージョンに至ったかを示す「割合」を示します。資料請求ページにおけるCVR算出の式は、以下です。
CVRは、Webサイトやランディングページ、広告施策などの効果を定量的に評価するための指標として広く活用されています。
CVRが低い場合、ユーザーのニーズを解決できていなかったり、ユーザーが次の行動を取りやすくする工夫不足などの課題が潜んでいるかもしれません。逆に、CVRが高くても、そもそもCV数が極端に少ない場合は「ページの訪問者数」つまり流入に課題があるかもしれません。
つまり、CVRはあくまで「割合」であるため、訪問数やCV数が適切であるか、あわせて成果判断していきましょう。
業界別の平均コンバージョン率(CVR)
コンバージョン率(CVR)は、ボトルネックを発見する重要な手掛かりです。自社の数値推移を確認することはもちろん、業界平均値もベンチマークとなります。
参考までに、WordStreamが公開しているGoogle広告(米国)の業界別平均CVRは以下のとおりです。
- 検索広告の平均CVR:2.7%
- ディスプレイ広告の平均CVR:0.89%
業界だけでなく、流入経路や施策、商材によってもCVRは異なります。まずは自社の数値推移を把握しながら、改善の余地がないか確認していきましょう。
コンバージョン設計のポイントとKPIとの関係
コンバージョンは、Webサイトの目的やユーザーの検討段階によって「どの行動をコンバージョンとするか」は変わります。ここでは、そのコンバージョンをどのようにKPIに落とし込み、改善につなげていくべきかを整理します。
施策フェーズに応じたコンバージョンの設計
ユーザーは必ずしもすぐに「お問い合わせ」につながるとは限りません。
ホワイトペーパーのダウンロードやメルマガ登録など、興味関心レベルでの行動(マイクロコンバージョン)を含め、フェーズに応じて適切なコンバージョンを設計することが重要です。
こういったマイクロコンバージョンから接点をもった見込み客も、リード育成施策やインサイドセールスからのコミュニケーションで検討段階を引き上げることも可能です。
KPI設計におけるコンバージョンの位置づけ
コンバージョンは、KPI(重要プロセスの目標数値)としても活用されます。
KPIは、KGI(売上や受注などの最終目標)を実現するための中間指標であり、施策ごとの成果を可視化するためのものです。
例えば、今期売上1000万円というKGIから逆算して、マーケティング領域で「見込み客250人」というゴールを設定したとします。
その実現に向けて「ウェビナー申込数50件」「サービス資料ダウンロード10人」といった施策ごとのKPIを整理します。
施策単体の目標コンバージョンとしてだけでなく、マーケティング領域の目標進捗管理が明確になり、施策の評価・改善がスムーズにおこなえます。
 KPIは、【図解】KPIとは?意味や具体例、設定方法を簡単にわかりやすく解説の記事でも詳しく解説していますので、KPI設計のヒントにご活用ください。
KPIは、【図解】KPIとは?意味や具体例、設定方法を簡単にわかりやすく解説の記事でも詳しく解説していますので、KPI設計のヒントにご活用ください。
コンバージョン数の目標達成に向けたポイント
Webサイトのコンバージョン数を安定的に増やすには、ユーザーにとって使いやすい導線設計(UI/UX)」と「成果の測定・検証(データ分析)」の両輪が必要です。
特にBtoBサイトでは、少ないデータからでもユーザー行動を振り返り、段階的な改善を重ねていく姿勢が重要です。
成果を高めるためのUX/UI設計
コンバージョン数を高めるためには、ユーザーがスムーズにアクションを起こせるようなWeb体験(UX)と、わかりやすく整理されたインターフェース(UI)となっているか確認しましょう。
フォームが長すぎて離脱される、CTAが目立たない、導線が複雑など、UX上の課題はコンバージョンの低下につながります。
- ユーザーの疑問を先回りして解消するコンテンツ構成
- 自然な流れでページを読み進められる構成と情報の配置
- ストレスを感じにくいフォーム設計(入力項目の数や言葉づかい)
- CTAの文言やデザイン、配置の工夫
ユーザー視点で「コンバージョンしやすいWebサイトとなっているか」を常にチェックしていきましょう。
Webサイトにおける「UI」や「UX」については、次の記事でも詳しくご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
UIの意味をわかりやすく|UXとの違いとWeb担当者が押さえるべき改善ポイント
UX(ユーザーエクスペリエンス)とは?Webサイトにおける意味と成果を高めるチェックポイント
コンバージョン測定と定期的な振り返り
改善を始めるには、まず現状の成果を正しく把握することが不可欠です。Googleアナリティクスや広告ツールなどを使い、以下のような数値を定期的に確認しましょう。
- 月ごとのCV数とCVR
- チャネル別、ページ別のCV数とCVR
- マイクロコンバージョンの発生率(DL数、クリック率など)
とくに、リードの少ないBtoBサイトでは、短期的な数値だけで判断するのではなく、トレンドを見ながら中長期的に振り返ることが重要です。
ボトルネックの発見と改善のステップ
コンバージョンを改善するには、まず「どこでユーザーが止まっているのか」を把握することが重要です。例えば、次のような方法でユーザーの行動を把握し、ボトルネックの特定ができます。
- ヒートマップツールによるスクロールやクリックの動きの可視化
- フォーム分析による入力途中の離脱率の確認
- GA4の「探索レポート」などで、ユーザーの遷移状況や導線を把握
また、最終的なコンバージョンだけでなく、マイクロコンバージョンで、段階的な行動を定量的に評価するのも有効です。
大切なのは、データに基づいて仮説を立て、小さく検証を重ねる姿勢です。やみくもに変更するのではなく、ユーザー行動を踏まえた改善が成果につながります。
課題発見につながる「Webサイト簡易診断サービス」
正しい課題把握やボトルネックの発見が難しい場合、外部の診断を活用するのもおすすめです。タービン・インタラクティブでは、Webサイトの成果を改善するための簡易診断サービスを提供しています。
専門のアナリストが貴社のWebサイトのユーザビリティ評価やSEO対策状況、コンバージョン最適化、さらには競合他社との比較など、幅広い観点から診断をおこないますので、KPI設計の見直しや改善アプローチの整理に役立ちます。ぜひ、ご活用ください。
まとめ
自社の目的やWebサイト、マーケティングにあわせて「何をコンバージョンとするか」を明確にし、その成果がどのように生まれているのかを継続的に分析・改善していくことで、より成果につながるマーケティング活動が実現できます。
私たちタービン・インタラクティブでは、事業拡大に貢献するWeb戦略のご提案、サイト制作、CRMやマーケティングオートメーションの導入支援など多数の実績がございます。マーケティング活動の改善や、サイト制作・リニューアルをご検討の際は、ぜひ一度お声がけください。