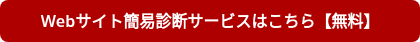なぜ今、Webサイトリニューアルを考える企業が増えているのか?
企業のWebサイトリニューアルは、通常4〜5年ごとにおこなわれることが多いといわれていますが、まさに今、BtoB企業でその動きが加速しています。その背景には、以下のような変化があります。
- コロナ禍で一時的に強化したWebサイトが、見直しのタイミングを迎えている
- 従来の運用体制やCMSが現在の業務フローに合わなくなってきている
- 営業活動のデジタル化、採用手法の多様化により、Webサイトの役割が広がった
さらに2025年現在、検索エンジンは従来のSEO対策だけでなく、生成AIによる検索体験(SGE)にも対応していく企業も多いでしょう。FAQやQ&Aコンテンツの充実、構造化データのマークアップといった施策が、自社のWebサイトを見つけてもらいやすくし、集客力を高めるポイントになります。
営業活動では、SFA(営業支援ツール)やCRM(顧客関係管理)とWebサイトを連携させることで、リード獲得からナーチャリングまでをWebで一貫しておこなう企業も増えてきました。また、採用活動においても、多くの求職者が企業の採用サイトを参考にしており、情報の信頼性や更新頻度が企業イメージに大きく影響すると言われています。
これらの変化により、「見直したほうがよさそうだけど、何から手をつければいいか分からない」と悩むWeb担当者の方も多いと思います。まずは、自社のWebサイトにどんな役割を期待しているか、その目的と現状を整理するところから始めましょう。
Webサイトリニューアルの必要性が高まるのはどんなとき?
Web担当者の立場から見て、自社のWebサイトが次のような状態に当てはまる場合は、リニューアルや改善を検討するタイミングといえます。
- Webサイトが前回の制作から5年以上経っている
- ナビゲーションや全体構成が使いにくく、情報が探しづらい
- コンテンツの更新ができておらず、製品情報などが最新化されていない
- Webサイトへのアクセスやお問い合わせが減っている
- サイトのデザインやブランドの印象が古く、企業イメージと合っていない
課題が複数見つかることもあるでしょう。次にリニューアルが必要かどうかを判断するための具体的な視点を解説していきます。
Webサイトの見直しは「顧客の行動」と「社内運用」の観点から考える
Webサイトを見直す際は、大きく分けて次の2つの観点から検討するのが効果的です。

1. 顧客に向けて情報を伝え、行動を促す観点
製品・サービスの紹介やお問い合わせ、採用情報など、Webサイトは顧客や求職者との接点となる重要なツールです。この観点では、「訪問者が必要な情報にスムーズにたどり着けるか」「行動(コンバージョン)を起こしやすい設計になっているか」といった点を見直します。
2. 社内で効率よく情報を更新・活用する観点
Webサイトは作って終わりではなく、継続的な運用・改善が前提です。この観点では、「CMSなどの更新ツールが使いやすいか」「社内で誰がどう管理するかの体制が整っているか」など、日常的な運用のしやすさを見直します。
この2つの観点で現状を整理することで、「どこに課題があるのか」「どの範囲で改善が必要なのか」が明確になってきます。次に、それぞれの課題が見えてくる典型的なケースをご紹介します。
1. スマートフォン対応などの使いやすさやデザインが古くなったとき
 まずは、訪問者にとっての使いやすさが重要です。たとえばスマートフォンでの表示が崩れている、文字が小さい、ボタンが押しにくいなどの問題があると、ユーザーの離脱を招く原因になります。また、古いデザインやレイアウトのままだと、企業の印象にも影響を与えかねません。
まずは、訪問者にとっての使いやすさが重要です。たとえばスマートフォンでの表示が崩れている、文字が小さい、ボタンが押しにくいなどの問題があると、ユーザーの離脱を招く原因になります。また、古いデザインやレイアウトのままだと、企業の印象にも影響を与えかねません。
- スマートフォン表示が見づらい、レイアウトが崩れている
- ボタンや導線が直感的でなく、目的の情報にたどり着きにくい
- デザインが古く、ブランドの魅力が伝わっていない
UIやデザインは、単なるビジュアル改善ではなく、ユーザー行動を設計する戦略的なプロセスです。「誰に・何を・どのように行動してほしいか」という視点が重要であり、4つ目の成果にも関わる部分です。詳しくは、こちらの記事も参考にしてください。
詳しくはこちら:UIの意味をわかりやすく|UXとの違いとWeb担当者が押さえるべき改善ポイント
2. 事業内容や顧客ニーズの変化に、コンテンツが追いついていない
 事業領域の拡大や顧客ニーズの変化に伴い、Webサイトの情報が現在の状況に合っていないこともよくあります。
事業領域の拡大や顧客ニーズの変化に伴い、Webサイトの情報が現在の状況に合っていないこともよくあります。
- 製品やサービスが増えたのに、紹介ページが古いまま
- 注力すべき商材が変わっているのに、トップページや導線が過去のまま
- 採用強化を進めたいのに、求職者向けの情報が不足している
こうした状態では、ユーザーが欲しい情報にたどり着けず、他社サイトへ流れてしまう可能性があります。
とくに見込み客の課題や関心に合ったコンテンツが不足していると、アクセス数や、資料請求・お問い合わせなどのコンバージョン数の減少を招きかねません。結果として、本来獲得できたはずの商談や採用機会を逃しているケースも少なくありません。
そのため、最新情報の反映だけでなく、顧客の検索意図やニーズに合った情報設計ができているかを定期的に見直すことが重要です。
関連記事:コーポレートサイトとは?BtoB企業が成果を出すための役割・設計・運用を解説
3. 社内での運用・更新がうまくいっていない
 「発信したいのにできない」という課題は、外からは見えにくいものの、実は根深い問題です。前述した「コンテンツが追いついていない」原因が、更新の手間や体制の不備であることも少なくありません。
「発信したいのにできない」という課題は、外からは見えにくいものの、実は根深い問題です。前述した「コンテンツが追いついていない」原因が、更新の手間や体制の不備であることも少なくありません。
- CMSが古くて使いにくく、更新のたびに外注が必要
- CMSが導入されておらず、HTMLなど専門知識がないと更新できない
- 修正や情報追加に時間とコストがかかり、情報鮮度が落ちてしまう
- 社内の運用体制が曖昧で、誰が何を発信するか決まっていない
まずは、社内での役割や管理体制に課題があるか、更新作業に伴う技術的な問題かなど、ボトルネックを探しましょう。ツールや体制を見直すことで運用性を改善できるケースもあります。
詳しくはこちら:CMSとは?Webサイト運用の初心者が知っておきたい基礎知識・メリットを解説
4. Webサイトの成果が出ているのか、判断がつかないとき
 「成果が落ちている」という明確な変化だけでなく、「今の成果が良いのか悪いのかわからない」と感じているケースも多いのではないでしょうか。
「成果が落ちている」という明確な変化だけでなく、「今の成果が良いのか悪いのかわからない」と感じているケースも多いのではないでしょうか。
- 他社と比べて自社サイトのお問い合わせ数は適正なのか?
- 本来もっと成果を出せる余地があるのでは?
- 成果が出ていない理由は、Webサイトの問題か運用の問題か?
こうした疑問を感じた場合は、アクセス解析や競合比較などの現状分析を通じて、課題の整理から始めるのがおすすめです。
成果につながらない理由を整理するには?
「アクセスはあるのに成果が出ない」「お問い合わせが少ない」といった課題に対して、どこに原因があるのかを正しく把握することが重要です。
たとえば、次のような分析視点から「どこにギャップがあるのか」「何を変えるべきか」を整理しやすくなります。
- アクセス解析で離脱ポイントや流入元を把握する
- ヒートマップでユーザーの行動を可視化する
- コンバージョン導線の設計を確認する(CTAの位置・文言など)
- 社内ヒアリングで営業や採用担当の声を集める(よくある質問や失注理由など)
関連記事:Webサイト改善点を洗い出す!課題抽出の基本ステップと4つの方法
自社内での分析が難しい場合は、Webサイト診断などの支援サービスを活用するのもひとつの手です。課題を正しく把握できれば、リニューアルが必要か、改善で十分かの判断もしやすくなります。
当社が提供している「Webサイト診断」も是非ご活用ください。専門のアナリストが貴社のWebサイトを多角的に分析し、ユーザビリティ評価やSEO対策状況、コンバージョン最適化、さらには競合他社との比較など、幅広い観点から診断をおこないます。
「改善かリニューアルか?」を判断するポイント3つ
Webサイトの課題を整理するには、「何が原因で、どの範囲に影響しているのか」を見極めることが大切です。ここでは、課題のタイプに応じて「リニューアルが必要か、改善で十分か」を判断するための3つの視点を紹介します。
1.Webサイト全体に関わる構造的な課題なら、サイトリニューアルが必要
次のようなWebサイト全体に関わる構造的な課題がある場合は、部分的な対応では限界があります。この場合はWebサイト全体を一から見直す、リニューアルがおすすめです。
- ナビゲーションや導線が使いにくく、ユーザーが必要な情報にたどり着きにくい
- コンテンツが増えすぎて、情報が整理されていない
- Webサイト全体のトンマナやビジュアルが古く、企業のブランドイメージと合っていない
目的・ターゲットに立ち返ったうえで、構成設計や導線、デザインを含めた抜本的なリニューアルができますので、UX改善・DX推進・採用強化・動画やAI対応など、課題の本質とともに、顧客にとっても自社にとっても最適なWebサイトを制作することができます。WebサイトリニューアルはPR戦略として活用できる点も考慮するとよいでしょう。
関連記事:ホームページ(Webサイト)リニューアルの進め方と成功事例
2.コンテンツ増加や部分的なUI変更なら、サイトの部分改修で対応
課題が「特定のページや導線」に限られている場合は、Webサイトをフルリニューアルせずとも部分改修で改善できる可能性があります。
- CTA(お問い合わせボタンなど)の配置や導線がわかりにくい
- 採用情報や製品紹介ページの内容が古くなっている
- Webサイトの更新作業に手間やコストがかかる
例えば、HubSpotなどのCMSツールを導入すれば、専門知識がないメンバーでもWebサイトの更新が可能になります。製品情報の追加や採用情報の変更などをスピーディーに反映できるため、常に最新の状態を保つことに役立ちます。
 また、現状のWebサイト構成を大きく変えずに、ランディングページを追加することで、集客導線やコンバージョン導線を強化することもできます。ただ、乱立してしまうとWebサイト内の構造が複雑になり、ユーザーが情報を探しづらくなるので、単体追加が全体設計を見直すべきかは気をつけましょう。
また、現状のWebサイト構成を大きく変えずに、ランディングページを追加することで、集客導線やコンバージョン導線を強化することもできます。ただ、乱立してしまうとWebサイト内の構造が複雑になり、ユーザーが情報を探しづらくなるので、単体追加が全体設計を見直すべきかは気をつけましょう。
 このように必要な箇所を優先的に見直すことで、コストやスケジュールを抑えて成果の改善が期待できます。
このように必要な箇所を優先的に見直すことで、コストやスケジュールを抑えて成果の改善が期待できます。
優先順位に迷ったら、ROI視点での判断を
課題が複数見つかり、「どこから手をつけるべきか」迷う場合は、費用対効果(ROI)の視点も判断材料になります。リニューアルにかかるコストと、得られる効果のバランスを見極めることも重要です。
- 改善・リニューアルによって、どのくらいリード数や採用数が増える見込みか?
- CMS導入によって、更新作業の工数削減や運用負荷軽減につながるか?
- ブランド刷新によって、企業の信頼性・イメージがどのように向上しそうか?
たとえば、フルリニューアルには数百万円〜数千万円かかる場合もありますが、限られた予算やリソースの中でも成果を出したい場合は、前述した一部の改修から始めるのも現実的な選択肢です。
もちろん、サイト全体のブランド刷新や構造的な課題に対応する場合には、フルリニューアルだからこそ得られる大きな効果もあります。
コストだけで判断するのではなく、想定される成果の規模やKPI、解決したい課題の影響範囲や重要度を踏まえたうえで、自社にとって最適な方法を検討しましょう。
関連記事:【図解】KPIとは?意味や具体例、設定方法を簡単にわかりやすく解説
3.目的や成果判断に課題なら、Webサイト戦略設計の見直しから
意外と見過ごされやすいのが、Webサイトで「何を目的とし、どのような成果を得たいのか」が社内で十分に整理されていないケースです。この場合は、まず戦略設計から見直すことが重要です。
- Webサイトの目的が曖昧で、社内でも共通認識が持てていない
- 成果を何で測るか(KPI)が定まっていない
- どんな情報を届けるべきかが明確になっておらず、更新が滞っている
いきなりデザインや構成を変えるのではなく、まずは「Webサイトに何を期待するのか」という戦略や方針の整理をすすめましょう。「誰に・何を・どんな行動につなげたいのか」といった基本設計を見直すことで、リニューアルの方針も自然と定まっていきます。 関連記事:【初心者向け】BtoBマーケティング戦略立案と実行の基本ステップ
関連記事:【初心者向け】BtoBマーケティング戦略立案と実行の基本ステップ
Webサイトの目的や成果判断が曖昧な場合のヒント
「まずは戦略整理から」と判断された方に向けて、社内での目的共有に役立つ視点をご紹介します。
部門ごとの目的や成果から考える
Webサイトの目的は1つではありません。部署ごとに期待される役割を整理することで、「本当にリニューアルが必要なのか」「どの部分を重視すべきか」が明確になります。
まずは、コーポレートサイトに求める各部門の主なニーズをみていきましょう。

マーケティング・営業部門
- お問い合わせや資料請求につながる導線が整っているか?
- 導入事例や製品・サービスの紹介が十分に伝わっているか?
主なターゲット:見込み客や既存顧客
主なKPI:訪問者数、検索流入数、リード数、商談獲得数など
人事・採用部門
- 求職者に信頼や共感を持ってもらえる情報があるか?
- 社員インタビューや働く環境、福利厚生などが丁寧に紹介されているか?
主なターゲット:新卒・中途の求職者
主なKPI:ページ閲覧数、採用エントリー数など
経営・広報部門
- 企業理念やビジョン、社会的な取り組みなどが明確に伝わっているか?
- 投資家や取引先など、ステークホルダーが信頼できる内容になっているか?
主なターゲット:株主、取引先、メディア、自治体など
主なKPI:ページ閲覧数、PV数、シェア数など
このように、部門ごとの視点を整理することで、「誰に・何を・どう届けるか」が明確になります。リニューアルの必要性や優先順位を判断しやすくなるだけでなく、社内の合意形成も進めやすくなるでしょう。
整理した目的や課題をどう活用するか
目的や課題を整理したあとは、それをもとに次のアクションを検討します。
1.KPIの設定に課題がある場合
Webサイトの目標が曖昧なままだと、改善の方向性も見えにくくなってしまいます。まずは部署ごとに、お問い合わせ件数・採用エントリー数など、Webサイトで達成したいKPIを明確にしましょう。各目標と現状のギャップから不足している掲載情報やコンテンツ、オファーを洗い出すヒントになります。
2.設計や構成に課題がある場合
Webサイトに求める役割をふまえて、サイトマップの見直しや情報設計を再構成しましょう。リード獲得のためのオファー資料、採用の強化が必要ならば「求職者向けのコンテンツを追加」などが考えられます。必要なもの、今後追加していくものなど優先度とともに整理します。
3.運用体制や更新方法に課題がある場合
管理・運用体制フローの整理、CMSやマーケティングオートメーションなどの支援ツール導入など、ひとつひとつ検討します。成果につながるWebサイトは更新し続けることも重要なので、「予算にあわせたツールを検討」ではなく、自社の本質的な課題解決に必要な範囲を考えると良いでしょう。
戦略的にリニューアルを進めるためには、こうした整理がスタートラインです。目的によって次のステップは変わるため、1つに絞る必要はありません。むしろ、複数の方向性を検討したうえで、優先順位をつけて着手することが、成果につながる近道になります。
また、現状のWebサイト構成を大きく変えずに、ランディングページを追加することで、集客導線やコンバージョン導線を強化することもできます。ただ、乱立してしまうとWebサイト内の構造が複雑になり、ユーザーが情報を探しづらくなるので、単体追加が全体設計を見直すべきかは気をつけましょう。
このように必要な箇所を優先的に見直すことで、コストやスケジュールを抑えて成果の改善が期待できます。
関連記事:【初心者向け】BtoBマーケティング戦略立案と実行の基本ステップ