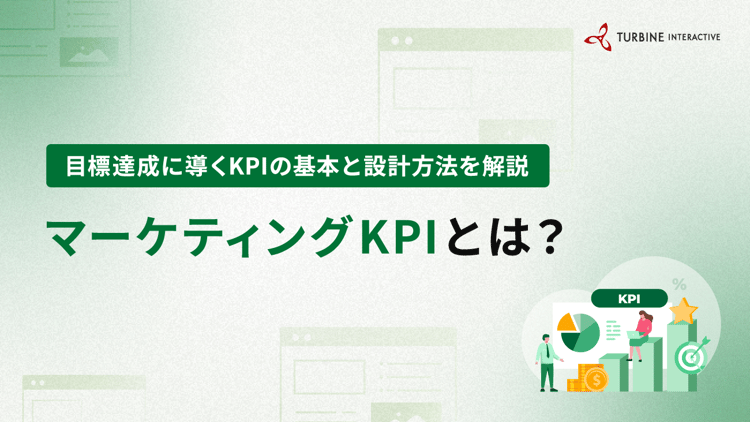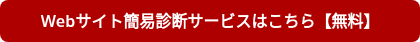KPIは、マーケティング活動の進捗や成果を見える化し、チームの判断や改善を支える大切な指標です。しかし「設定しているのに、事業成果に貢献している実感がない」と悩む声も少なくありません。
本記事では、KPIが機能しない理由を構造的に解説し、BtoBマーケティングにおけるKPI設計・運用のポイントを具体的に紹介します。成果につながるKPI設計のヒントをお探しの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
KPIを追っているのに、目標達成につながらないのはなぜ?
KPIを設定し、マーケティング施策を実行しているにもかかわらず、「事業目標の達成につながらない」「営業や経営層からの評価を得られない」といった悩みを抱える担当者は少なくありません。
KPIが機能しない原因は、構造設計が不十分だから
マーケティングに求められる本来の役割は、個々の施策で成果を出すことではなく、「売上」や「新規顧客の創出」といったKGI(重要目標達成指標)に貢献することです。営業やインサイドセールスと連携し、マーケティング活動をどう事業目標に結びつけていくかを設計する必要があります。
しかし、KPIとKGIのつながりが曖昧なまま数値を追っているケースも少なくありません。これは「KPIを設定していても目標達成につながらない」最大の原因となります。
たとえば、前年の延長で「MQL数」や「資料DL数」をKPIとして据えても、それが今年のKGI達成に向けて本当に意味のある指標なのか、検証されていなければ効果的とは言えません。KPIを起点に考えるのではなく、KGIから逆算してプロセスを分解し、構造的に設計することが重要です。
関連記事:成果が出ない理由はここだ!自社マーケティング活動の落とし穴と解決法【前編】
KGI・CSF・KPIの関係と役割
KPI(重要プロセスの目標数値)とは、事業目標の進捗と課題を可視化するための指標です。本来、KGI(重要目標達成指標)と明確につながっていることが前提となります。
KGI(重要目標達成指標):会社として最終的に達成すべき目標数値
CSF(重要成功要因):KGIを実現するために不可欠な重要プロセス
KPI(重要プロセスの目標数値):CSFを実現するために追うべき目標数値
このようにKGIを起点に、「その達成に必要なプロセスは何か(CSF)」「それをどう測定するか(KPI)」を逆算して整理する必要があります。

たとえば、「来期の売上を1.2倍にする」というKGIがある場合
-
MQLをいくつ創出すればいいか?
- そのためにどんな施策に取り組むべきか?
- どの指標を追えば、進捗が見えるのか?
こうした逆算思考が、戦略的なKPI設計の基本です。
KPIを「評価のための数字」ではなく、「目標達成のための共通言語」として活用することで、マーケティング活動はより戦略的に機能し、全体最適につながる運用が可能になります。
KPIの意味や基本は、こちらの記事「【図解】KPIとは?意味や具体例、設定方法を簡単にわかりやすく解説」でも詳しく紹介しています。
KGIから逆算するマーケティングKPI設定手順
ここでは、マーケティングKPIは「KGI達成のためのプロセスの一部」であることを踏まえ、段階的に目標を分解しながら、重要なプロセス(CSF)、具体施策、指標(KPI)を整理していく「成果につながるKPI設計方法」を解説します。
1. 事業最終ゴールの目標数値(KGI)から逆算する
まずは、自社全体のゴールからマーケティングが担う役割を明確にすることが必要です。KGIを事業全体から段階的にブレイクダウンしていくと、マーケティング部門のKPIがどこに位置づくのかが整理できます。
2. 重要なプロセス(CSF)を明確にする
マーケティングのKPI「MQLを100件創出する」を達成するためには、マーケティング活動の中でどのようなプロセスが成功の鍵を握るかを明確にする必要があります。これが CSF(Critical Success Factor) です。KFS(Key Factor for Success)と表現されることもありますが、ほぼ同じ意味で「KGIの達成において鍵となる重要な成功条件」を指します。
マーケティングKPI設計における CSF は、施策(手段)ではなく「プロセス上の成功条件」 を指します。
BtoBマーケティングでは、見込み客の検討段階に応じて施策の役割が変わります。このファネル構造に沿って整理するとよいでしょう。
マーケティング施策のファネル構造に照らし合わせることで、各プロセスに応じたKPIの設計基準が明確になり、成果に直結する指標の選定がしやすくなります。
3. 取り組むマーケティング施策の決め方
CSFが整理できたら、それぞれのプロセスを進めるために有効な施策を選定します。マーケティング施策を分類すると、以下のようになります。
たとえば、CSF「有望な見込み客との接点を獲得」に対しては、ホワイトペーパーの提供やウェビナーの開催といった、リード情報の取得に直結する施策が該当します。また、「情報提供を通じて興味関心を育成」プロセスでは、ブログ記事やメールマガジンなどのコンテンツ施策が有効です。
マーケティング施策選定のポイント
しかし、多くのマーケティング活動では、どのプロセス(CSF)も必要といえます。むやみに施策数を増やすのではなく、まずは次の視点で整理し、重要なKPIと施策の優先度を明確にしましょう。
選定する施策は、以下のような視点で優先度を見極めるとよいでしょう。
-
今、特にどのプロセスに注力すべきか?
-
自社の強みや、予算・人的リソースに適しているか
-
短期的 or 中長期的に成果が見込めるか
-
その施策が他のプロセスや活用しているツールと連携しやすいか
また、目先のCVを重視した短期的な施策ばかりに偏らないことも大切です。広告やLP改修など、コンバージョンを直接狙う施策は即効性がありますが、将来的なリード獲得につながる認知拡大や潜在層との接点づくりといった中長期的なマーケティング活動とあわせて進めることで、施策全体の持続性と成果を高めることができます。
関連記事:Webサイト改善点を洗い出す!課題抽出の基本ステップと4つの方法
4. マーケティング施策のKPIを設定する
重点施策が決まったら、それぞれの施策がCSFにどう貢献するかを明確にし、達成状況を測るKPIを設定します。その際、事業のKGIからつながる「成果に直結する指標」として設計されているかどうかを、常に念頭におきましょう。
コンテンツ内容によるKPIの違い
ひとくちにホワイトペーパーのダウンロード数がKPIといっても、コンテンツ内容と対象フェーズによってKPIがどのように変わるかを整理した例を紹介します。
このように、KPIは単に「施策に紐づく数値」で決めるのではなく、施策の目的や成果をふまえて設定することが重要です。
KGIからの逆算をもとに、「この施策でどのCSFに貢献し、どのような成果を期待しているのか?」を明確にすることで、適切なKPIが見えてきます。
5. KPIの評価期間と達成基準を設定
KPIは、チームの動きを定量的に見える化するための重要な指標ですが、「何のための数値か」「どのくらいで成果とみなすか」が曖昧なままだと、形だけの運用になりがちです。
継続的に実施するブログや資料DL施策は、月次や四半期ごとに進捗を確認し、改善の打ち手を検討します。一方で、短期的なキャンペーンやイベント施策は、実施終了後にまとめて効果検証を行うのが一般的です。
このようにKPIの定義とあわせて、明確な達成基準と評価サイクルを設けておくことが、改善と成果につながるKPI運用への第一歩となります。
KPIを成果につなげる運用のポイント
KPIは、設計した時点では「仮説」にすぎません。大切なのは、KPIの進捗を定期的にモニタリングし、課題に応じて柔軟に改善していくことです。
KPIは定期的なモニタリングと改善が必要
たとえば、「ホワイトペーパーのダウンロード数」をKPIにしていても、数値が上がらない場合は以下のような問いが必要です。
- 十分な流入はあるか?(セッション数)
- CTAは見られているか?(表示回数・クリック率)
- フォームに離脱要因はないか?(入力完了率)
このように、KPIが目標に届かないときに「原因を探るための関連指標」を見ていくことで、具体的な改善施策が見えてきます。
KPIは関連する行動指標とセットで運用する
KPI単体の数値では、ボトルネックや改善点を見落としやすくなります。そのため、KPIと併せて定点観測すべき行動指標(サブ指標)を設けておくことが重要です。
ページ滞在時間やスクロール率などの行動指標は「関心度の高さ」や「コンテンツ理解度」を把握する上で参考になりますが、CV率の改善要因としては補助的な扱いになります。
KPIの「数」を達成しているのに「質」に課題がある場合
たとえば「マーケティングのKPI」であるMQLは達成したのに、インサイドセールスでのSQL化が芳しくなかったとします。数値目標は達成したのに、質に課題がある場合です。
この場合、2つの視点で振り返ることが大切です。
ギャップ要因を見直す
成果が上がらない原因を探る際、「導線が悪いのか」「コンテンツが響いていないのか」など、さまざまな要因が考えられます。
MQLに大きく貢献したホワイトペーパーのダウンロード数があったとします。接触したリードにとってはニーズの高いテーマだったにもかかわらず、「自社の製品を検討する層のマッチ率が低い」などの要因が考えられます。コンテンツの中身や、広告などの誘導施策を見直していきましょう。
達成基準の「質」について条件を見直す
インサイドセールスや営業部門で有効に「活用できる状態」であるかどうか、その条件を明確に決めておくことで、部門間の連携が円滑になります。
 このように、KPIは常に「何が成果につながっているのか」「次のKPIに貢献できているか」と俯瞰した観点を持つことが、事業目標達成において非常に重要です。
このように、KPIは常に「何が成果につながっているのか」「次のKPIに貢献できているか」と俯瞰した観点を持つことが、事業目標達成において非常に重要です。
目標達成のためのKPI設計、正しくボトルネックを把握しよう
設定したKPIは、課題の本質をとらえているか?
KPIが本質的なボトルネックに向き合えているかを定期的に確認することが重要です。成果が上がらない原因を探る際、やみくもに指標を見ても、適切な改善にはつながりません。
重要なのは、自社のファネルのどこが滞っているか=どこにボトルネックがあるかを見極めたうえで、適切なKPIを設計することです。たとえば、認知の獲得が課題であれば「目標キーワードからの流入数」、検討段階への育成が課題であれば「ホワイトペーパーダウンロード後のCV率」など、フェーズごとに見るべき指標は異なります。
KPIの見直しに迷ったら、簡易診断サービスも活用を
KPIを設定したものの、「正しく設計できているのか分からない」「どこが課題なのか判断がつかない」と悩むこともあるでしょう。そうしたときは、第三者の視点を取り入れるのも有効です。
タービン・インタラクティブでは、Webサイトの成果を改善するための簡易診断サービスを提供しています。専門のアナリストが貴社のWebサイトのユーザビリティ評価やSEO対策状況、コンバージョン最適化、さらには競合他社との比較など、幅広い観点から診断をおこないますので、KPI設計の見直しや改善アプローチの整理に活用いただけます。
「KPIがうまく機能していない気がする」「どこにボトルネックがあるか整理したい」と感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
マーケティングKPIは、施策の成果を可視化し、組織として目標に向かって前進するための重要な指標です。しかし、数値を並べるだけでは機能せず、戦略やプロセスに基づいて構造的に設計・運用することが求められます。
私たちタービン・インタラクティブでは、Web戦略の立案からKPI設計、サイト改善、CRMやマーケティングオートメーションの活用支援まで、BtoB企業のマーケティングを伴走型でご支援しています。
「KPIを設定しているのに成果が見えない」「施策が点在して効果測定が難しい」とお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。